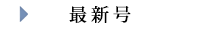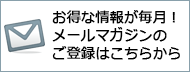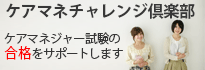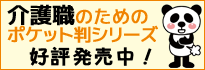|
|
「患者やその家族の立場で考えろ」 父が命をもって教えてくれた |
|
看護師として懸命に仕事をしていたある日突然、父の闘病が始まった。 自らが患者の家族という立場になって初めてわかったこと、 気がついたことがたくさんある。 それは、父が自分の闘病と死をもって教えてくれたことだ。 清水 里香子 さん (福岡県 33歳 看護師) |
|
がん告知に「俺も兄貴と同じか。 仕方ないたい・・・」と笑う父 父の病気が判明したのは約2年前のことでした。両親の人生はまさにこれからだと、ありふれた幸せを満喫していた時でした。父が背中の痛みを訴えたのです。 いろいろな検査を受けた後、「先生が(私と)話したいと言っている」と父から電話が入りました。 嫌な感じがしながら電話をすると、父のすい臓あたりに腫瘍のようなものがあると聞かされました。 その前年に父は自分の兄をすい臓がんで亡くしたばかりだったのに、「父までもがすい臓がん・・・」と、頭の中が真っ白に。 それでも私は医療従事者だと何とかこらえて、必死に話を聞きました。 父は長崎、私は福岡と離れた場所に住んでいたため、どこで治療をするかなどの相談をしました。 これから、がんの治療を進めるためには告知は必須。しかも、父の体を襲う痛みはひどくなっている。 一刻も早い治療選択が必要でした。しかし、父を前にすると涙が止まらなくなるだけでした。 父はまだ53歳。今まで真面目に働いてきて、本当にこれからという時になぜ?という思いと、治療を始めればどういう苦しみが父を襲うのかが目に浮かんだのでした。 どういう選択にしろ父の人生なのだから自分で知る必要があるし、自分で選ぶ権利もある。 家族で話し合い、父は医師から告知を受けました。 その時の光景を忘れることはできません。父は「俺も兄貴と同じか・・・」と言った後に、よちよち歩きの私の息子をあやしながら寂しそうに笑い、「仕方ないたい」と。 私は涙をこらえ、今後の治療について父と話をしました。 父は別の病院でセカンドオピニオンを受ける時にも自分のことだからと一緒に話を聞きました。 「どういうことだ」と 医師に詰め寄った親族 父の場合、手術での治療は不可能であり、抗がん剤で治療することになりました。 それからが父にとって長くつらい闘病の始まりであり、私たち家族にとっても闘いの始まりでした。 約1カ月の入院治療後、外来治療となり、1~2週に1回、福岡で治療を受け、あとは長崎に帰りました。 私は働きながら、治療の前後に私の家に宿泊する父を迎え、夜勤の前後で通院に付き添いました。 父は本当に強く、痛みやつらさを訴えることはほとんどありませんでした。 そんな父を見て、「看護師の私がしっかりしなければ。これからは決して泣くまいと心に誓いました。 「両親のおかげで看護師になれた。その力を今、発揮できなくていつ発揮するのだ」と何度も言い聞かせて。 それでも、病状が悪化していると言われた時など、動揺して何を言われたかわからなくなることも。 そこで父の先の状態を想定して、どう対応していけばよいかを、がんの治療に携わる先輩や友人に相談しました。 そんな日々が半年以上過ぎ、父は抗がん剤の副作用で徐々に食事をとることができなくなり、体力も落ちていきました。 治療を一時中断し、自宅に戻ったものの、すぐに病院に戻ることになりました。 既に厳しい状況だったのです。主治医から「これ以上、治療はできない」と伝えられました。 「どういうことだ」と医師に詰め寄る弟と叔父に、私は必死に父の病状をかみ砕いて話し、これからどうすべきか、私の考えをみなに伝えました。 「最期は長崎に帰りたい」。父はいつもそう話していました。体力や病状から考えても、今、帰るしかない。 でも、「帰る」と伝えることは、もう最期だと父に宣告するようなもの。 それでも、私は父に言いました。「長崎に帰ろうよ」と。父は寂しそうに「お前がそう思うなら帰ろう」と・・・。 寝台タクシーを手配し 父と最期の帰郷  機械や点滴につながれた最期は嫌だと言っていた父や、苦しんで逝ってほしくないという母の強い希望もあり、自分らしく静かに最期を迎えられる場所として、ホスピスを探しました。
候補のホスピスで先生の話を聞いて、実家が見える部屋を見せてもらい、弟も賛成してくれました。
機械や点滴につながれた最期は嫌だと言っていた父や、苦しんで逝ってほしくないという母の強い希望もあり、自分らしく静かに最期を迎えられる場所として、ホスピスを探しました。
候補のホスピスで先生の話を聞いて、実家が見える部屋を見せてもらい、弟も賛成してくれました。
そんな矢先、病院から電話が入りました。 「がん細胞が腹水まで広がっていて状態が厳しくなっている、明日になったら、帰れるかわからない」と。 すぐに福岡に戻った私は、寝台タクシーを手配し、父と息子(父にとっては孫)と長崎に帰りました。 寝台タクシーの車内では私はなるべく明るい話をして、痛む父の背中をさすりながら横を向いて泣いていました。 父も話しながら泣いていたのかもしれません。 何度往復したかわからない福岡~長崎間。通い慣れた道ですが、この約2時間は今までで一番長い道のりのように感じました。 ホスピスに到着すると父は「無事に着いて安心した」と話し、すぐに持続注射による鎮痛が施されると、吸い込まれるように眠りにつきました。 ホスピスでは「あなたはもう娘さんに戻っていいですよ。自分が看護師であることは忘れて大丈夫ですからね。 残された時間を大切に過ごしてください」と声をかけてもらいました。 私は父の娘というよりは、医療従事者として医師と家族の間に立ち、常に自分が冷静であるように努め、家族にわかりやすく説明したり指示したりしてきたのでした。 その一言で私は肩の荷を下ろし、ホッとしていました。それだけ私には気負いがあったのかもしれません。 そして、長崎に着いた翌日、父は家族、多くの友人に囲まれて亡くなりました。 看護師として何より大事なのは 患者や家族の心のサポート 父の闘病を通して、私は多くのことを学びました。看護師としても、人間としてもとても大切なことでした。 医療者の説明は非常にわかりにくいし、それをキャッチしサポートする看護師の力の大きさが求められます。 説明の補助だけでなく、気持ちもサポートすること、先を含めた必要な情報を適切な時期に提供すること、そのために膨大な知識や経験が必要であること・・・。 挙げればきりがありません。何よりも看護師として一番大切なのはその人の心を知ることです。 そして、予後がわかっている病気でも、家族の気持ちの整理は簡単にはできないもの。 2年たってもいまだに父のことを思うと涙があふれ出ます。この心のケアを大切にしていきたいと思います。 これから私は看護師という職業を天職として、来世で父に会った時に胸を張って話せるように、病める人、その周りの人のために日々働き続けていきたいと思います。 |
| ▼ 「読者体験手記」トップページにもどる |
| 「読者体験手記」は、『かいごの学校』(現在、休刊中)より掲載したものです。 |